タマフル秋の推薦図書特集の本をまとめています!
「宇多丸のウィークエンドシャッフル」(TBSラジオ)の恒例企画。大好きで毎回聴いています。
プレゼン力も大事なポイント。
- 『僕の名はアラム』
- 『プリズン・ブック・クラブ』
- 『アイアマンガー三部作1』
- 『すべての見えない光』
- 『永い言い訳』
- 『全裸監督 村西とおる伝』
- 『原節子の真実』
- 『休日ジャンクション』
- 『サピエンス全史』
- 『手話を生きる』
- 『金の国 水の国』
【伊藤聡の推薦図書】
『僕の名はアラム』
1940年出版された絶版だった連作短編を、村上柴田翻訳堂シリーズとして復刻。
翻訳の柴田元幸さん曰く、おじさんの話というジャンルにある。世の中とズレているおじさんだけど、子供は大好き。北杜夫やジャック・タッチなど。
本作もおじさんの話だ。9歳の男の子アラムが、ダメなおじさんと知り合っていく。伊藤聡さんおすすめは、メリックおじさんの短編。農場主になって石榴の木を植えようとするが、まったく計画性のない・・・。
『プリズン・ブック・クラブ』
刑務所内で読書会を開こうと試みを綴ったノンフィクション。
例えば囚人たちが、パキスタンとアフガニスタンに学校を作った人の自伝を読んだとする。内容は、建築資材を盗まれたりの試行錯誤だ。
「ドジなヤツだよ」「約束守るってすごいよな」「人を助けるのが怖い、だまされると思うと」といった感想からは、受刑者の人生が見えてくる。
受刑者たちには、結果を出したい、そんなときこそ古典を読んでほしいとアドバイスを送る。人生そのものが向上して最終的に役に立つ。
本の根源的な価値を伝えてくれる一冊でもあり、本が好きな人のための本。
『アイアマンガー三部作1』
イギリス小説。ゴシック版『千と千尋の神隠し』。
舞台は19世紀のロンドン郊外。ゴミで財をなした謎の一族がいる。その敷地内には、学校もあり病院もある。
みなそれぞれ、「誕生の品」を持っていて、死ぬまで肌身離さず持っていないといけない。なくすと災いが起こる。主人公は、お風呂の栓が誕生の品。
『すべての見えない光』
アンソニー・ドーア著。舞台は、1944年のヨーロッパ。ナチスのドイツ兵と目が見えないフランスの少女の物語が紡がれていく。
作家の円城塔が「世の中にはまれに、読み終えるのが惜しい小説がある」と推薦。
『永い言い訳』
映画監督の西川美和が、自作をノベライズ。映画もおすすめしていた。
【宇多丸の推薦図書】
『全裸監督 村西とおる伝』
間違いなく面白い自伝。玉袋筋太郎さんも推薦しているそうだ。
『原節子の真実』
世代ではないけれど。昭和の歴史とともに、国民的女優の本当に姿に迫ることができそう。
『休日ジャンクション』
真造圭伍さんは業界内評価が高いのかも。大根仁さんが絶賛していた「森山中教習所」や「ぼくらのフンカ祭り」は読んでいて、良作だった。これも読みたい。
『サピエンス全史』
人類において3つの革命が起こった。それは認知革命、農業革命、産業革命である。人間は想像力があり、そのために発展した。宗教、貨幣、政治、未来予測・・・虚構が文明をもたらした。
本書はサピエンスとして歴史をたどりながら、「人類は幸せになったのか?」という命題に挑む。個々は幸せになっていない。種としては繁栄しているが、幸せとはイコールではないのではないか、というのが著者の主張だ。
農業革命が起こって医学が発展するまで、人類にとっては過酷な時代。狩猟時代は栄養が取れてたけど、農業革命で一箇所に集まって栄養が足りなくなった。
解説を聞いているだけで面白かった。じっくり読みたい。
『手話を生きる』
手話には2種類あるという。
「日本語対応手話」と「日本手話」だ。
「日本語対応手話」は、日本語を手話に置き換えただけ。単語をぶつ切りで高度な思考は伝わりづらい。「日本手話」は、自然なネイティヴに近い手話。高度で複雑で抽象思考もできる。
読唇術でなるべく聴者に近づけないといけないという固定観念があり、日本語対応手話が求められがち。手話教育において弊害となっているそうだ。
「日本手話」は、ある一定の年齢までにインストールしないといけない。聾者は知能が低いと見られていたのは、教育の問題だったと指摘する。
『金の国 水の国』
岩本ナオさんは短編の名手で、古川さんが絶賛。心の機微を繊細に描く作家さんのようで。読みたい。













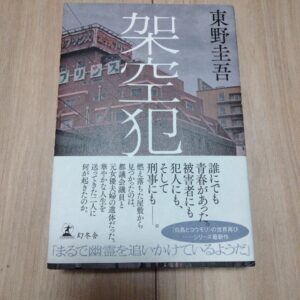
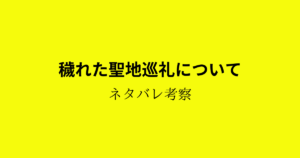

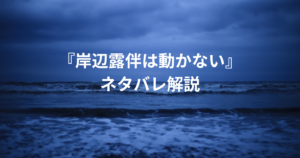

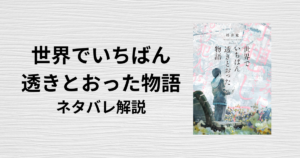
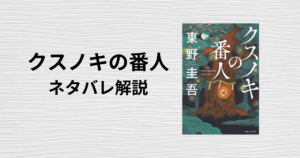

コメント